2007年04月29日
粘土で作る絵巻 つづき
昨日の土曜工作室の粘土の絵巻について”つくばねさん”から拡大写真を見たいとのコメントがありましたので掲載します。

左から火山の噴火、植物の誕生、太陽の恵み

石になったライオン、宇宙人の地球探索

山姥、虹、秋に群れ飛ぶトンボ

空から落ちてきたお尻、未来へのトンネル

左から火山の噴火、植物の誕生、太陽の恵み

石になったライオン、宇宙人の地球探索

山姥、虹、秋に群れ飛ぶトンボ

空から落ちてきたお尻、未来へのトンネル
Posted by 風車 at
21:53
│Comments(1)
2007年04月28日
粘土で作る絵巻
月末の週末は県立美術館実技室の「土曜工作室」のお手伝い。今回はゴールデンウイークの初日という条件もあって参加者はいつもより少なく、小学生10人ほどとその親御さんたちです。
机の上に立てかけられた高さ60cm、長さ180cmの板6枚に粘土を貼り付けて思い思いの絵を画いていきます。

途中で一度全員で作りつつある絵を見て、自分は何を画いたかを皆さんに説明します。それをインストラクターの方が聞いて、片側から物語を子どもたちと一緒に作成します。
今日は古代の噴火により木々が育つことから始まり、石でできたライオンや馬、江戸時代の山姥、現代の自動車、宇宙から落ちてきたお尻、未来へのトンネルという約10mの絵巻が出来上がりました。

作製時間は約3時間ですが、出来上がった作品の前で記念撮影をして、こわします。子供さんたちはちょっと残念そうな表情を見せますが、「次はもっと難しいものを作りたい」、「もっと大きなものを作りたい」、「また来月も来たい」など言いながら片付けを行います。床に落ちた粘土もきれいにふき取って今日の講座の終了です。
来月5/26(土)は素材探検「布を使って”くも”?になってみたい」がテーマです。お手伝いをする私にとっても"どんなことをするのか"楽しみです。
机の上に立てかけられた高さ60cm、長さ180cmの板6枚に粘土を貼り付けて思い思いの絵を画いていきます。

途中で一度全員で作りつつある絵を見て、自分は何を画いたかを皆さんに説明します。それをインストラクターの方が聞いて、片側から物語を子どもたちと一緒に作成します。
今日は古代の噴火により木々が育つことから始まり、石でできたライオンや馬、江戸時代の山姥、現代の自動車、宇宙から落ちてきたお尻、未来へのトンネルという約10mの絵巻が出来上がりました。

作製時間は約3時間ですが、出来上がった作品の前で記念撮影をして、こわします。子供さんたちはちょっと残念そうな表情を見せますが、「次はもっと難しいものを作りたい」、「もっと大きなものを作りたい」、「また来月も来たい」など言いながら片付けを行います。床に落ちた粘土もきれいにふき取って今日の講座の終了です。
来月5/26(土)は素材探検「布を使って”くも”?になってみたい」がテーマです。お手伝いをする私にとっても"どんなことをするのか"楽しみです。
Posted by 風車 at
20:50
│Comments(1)
2007年04月27日
サクラエビ
久しぶりの好天に誘われて、妻と東海道・由比の宿場町を散策しました。
「正雪紺屋」は由比正雪の生家?とも言われていますが、昔の染物に使った数個の大きな壷が残っていました。また天井には防火用の道具が吊り下げられており、火の用心への配慮に気を配ったことが伺われました。先日読んだ諸田玲子さんの「挫漁の人」の短編の中に由比正雪の話があったのでこの家の意味や背景は良くわかりました。
道を隔てた前は由比本陣跡できれいな公園です。この横にある東海道由比交流館でびっくりするものを見ました。生きた「サクラエビ」です。

水槽に入れられた小さなサクラエビは皆下を向いていました。これは①深海魚なので下に行きたがっている ②昼間は砂や泥にもぐっているので、潜ろうとしている ③水槽の中は普段生息している深海より水流があるので、下にいて平衡感覚を保っている などの理由が考えられるとのことです。
かわいい生きたサクラエビを見たあとなのでちょっと気が引けますが、サクラエビのかき揚丼を忘れるわけにはいきません。由比漁港によって食べてきました。

2つのかき揚が載って600円でした。また昨年は売り切れていた「沖あがり」(写真の左)も食べました。これは漁師の料理で、サクラエビ、豆腐、ねぎを煮込んだものでなかなかの味でした。
帰りの電車の中興津付近でふりかえると富士山が見えました。富士山も久しぶりに見た感じです。
「正雪紺屋」は由比正雪の生家?とも言われていますが、昔の染物に使った数個の大きな壷が残っていました。また天井には防火用の道具が吊り下げられており、火の用心への配慮に気を配ったことが伺われました。先日読んだ諸田玲子さんの「挫漁の人」の短編の中に由比正雪の話があったのでこの家の意味や背景は良くわかりました。
道を隔てた前は由比本陣跡できれいな公園です。この横にある東海道由比交流館でびっくりするものを見ました。生きた「サクラエビ」です。

水槽に入れられた小さなサクラエビは皆下を向いていました。これは①深海魚なので下に行きたがっている ②昼間は砂や泥にもぐっているので、潜ろうとしている ③水槽の中は普段生息している深海より水流があるので、下にいて平衡感覚を保っている などの理由が考えられるとのことです。
かわいい生きたサクラエビを見たあとなのでちょっと気が引けますが、サクラエビのかき揚丼を忘れるわけにはいきません。由比漁港によって食べてきました。

2つのかき揚が載って600円でした。また昨年は売り切れていた「沖あがり」(写真の左)も食べました。これは漁師の料理で、サクラエビ、豆腐、ねぎを煮込んだものでなかなかの味でした。
帰りの電車の中興津付近でふりかえると富士山が見えました。富士山も久しぶりに見た感じです。
Posted by 風車 at
19:21
│Comments(1)
2007年04月26日
ご当地検定・クイズ
先日静岡弁について書いたところ二人の方からコメントをいただきました。
また、茨城の友人からは故郷・秋田の方言に関するメールをいただきました。秋田県のホームページには「秋田地方の方言についての検定」が載っているそうです。
3択形式で100問の問いがあるそうで、この友人は69点で不合格であったといっていました。問題の中には聞いたことのない方言も含まれていたようですので、秋田の広い範囲で使われた言葉であったでしょうし、多分故郷を離れて40年以上経っているであろう友人が7割近くを正解したことにむしろびっくりしました。
今、さまざまなことに関する「検定」がブームになっています。ひとつの事象を対象にしていろいろ勉強してみることも大切で、面白いと思います。
静岡市は葵、駿河、清水と3つの区から成り立っていますが、葵区では「葵イズ」なる小冊子を出しています。これは葵区に関する歴史、地理、統計値などをクイズとしたものです。
私は二十歳ぐらいまで葵区に住んでいましたが正解率は40%ぐらいでした。答の欄には説明が記載されているので"葵区を再認識"する上でそれがとても参考になりました。
このクイズは清水中央図書館で手にしましたが、多分、区役所他いろいろなところに置いてあると思いますので挑戦してみてください。
また、茨城の友人からは故郷・秋田の方言に関するメールをいただきました。秋田県のホームページには「秋田地方の方言についての検定」が載っているそうです。
3択形式で100問の問いがあるそうで、この友人は69点で不合格であったといっていました。問題の中には聞いたことのない方言も含まれていたようですので、秋田の広い範囲で使われた言葉であったでしょうし、多分故郷を離れて40年以上経っているであろう友人が7割近くを正解したことにむしろびっくりしました。
今、さまざまなことに関する「検定」がブームになっています。ひとつの事象を対象にしていろいろ勉強してみることも大切で、面白いと思います。
静岡市は葵、駿河、清水と3つの区から成り立っていますが、葵区では「葵イズ」なる小冊子を出しています。これは葵区に関する歴史、地理、統計値などをクイズとしたものです。
私は二十歳ぐらいまで葵区に住んでいましたが正解率は40%ぐらいでした。答の欄には説明が記載されているので"葵区を再認識"する上でそれがとても参考になりました。
このクイズは清水中央図書館で手にしましたが、多分、区役所他いろいろなところに置いてあると思いますので挑戦してみてください。
Posted by 風車 at
20:01
│Comments(0)
2007年04月25日
少し大きな構図にしました
4/19の大きさははがきサイズでしたが、同じ構図で220x125mmと少し大きな富士山を彫りました。

背景も同じですが、左上からの同心円状の木目を利用してみました。この画では結構明確に出ていますが、これは障子紙の残りを使って摺ったものです。薄い紙だと出てくるのですが、いつも使っている版画用の紙だとうまく出てきません。
今回はこの版木(3枚)と別に彫った版木を、順次組合わせて摺っていきます。出来上がり次第紹介します。

背景も同じですが、左上からの同心円状の木目を利用してみました。この画では結構明確に出ていますが、これは障子紙の残りを使って摺ったものです。薄い紙だと出てくるのですが、いつも使っている版画用の紙だとうまく出てきません。
今回はこの版木(3枚)と別に彫った版木を、順次組合わせて摺っていきます。出来上がり次第紹介します。
Posted by 風車 at
19:09
│Comments(0)
2007年04月22日
「ごせっぽい」
もともと静岡生まれだが、高校卒業後、大阪、東京、茨城で40年余りを過ごしてきたので、こちらに戻ってからご当地の方々の使う静岡弁が新鮮に聞こえてとても楽しい。
一昨日、県立美術館でのこと、ボランティアやそこにいた人たちと静岡弁の話になった。このような話になると、ある年齢以上の人たちは止まらなくなる。
このとき静岡で時々使われる「ごせっぽい」と言う方言の意味を今まで勘違いしていたことを知った。「清々しない」と思っていたのはまったく逆で「清々する」が正しいと教えられた。語源は「ごしょぽい」(御所ぽい)で"公家さんの清々とした所作"からきたそうだ。
もっともっと勘違いしている多くの言葉があるかもしれないと反省した。
昨日の朝日・天声人語に方言について次のような面白い記事があった。(抜粋)
"宮城県栗原市が市民憲章を制定することになった。方言で文案をつくったが、不評に頭を痛めている。〈眼(まなぐ) 光をにらみ…腹ん中 熱(あ)っつぐ熱(あ)っつぐ…おれらいま風を切って走る〉。
これを市民にはかると、「東北の暗さが強調される」「田舎っぽい」といった否定的な意見ばかり目立ったそうだ。
「土地の暮らしと歴史がこもった言葉で独自性を」と、5人の制定委員は意気込んだ。方言学者からは「すばらしい」と励まされた。ところが、肝心の市民の胸には、あまり響いて
いないようだ。"
なかなかユニークな発想と思いますが、どちらの意見に賛同するか、難しい問題です。
一昨日、県立美術館でのこと、ボランティアやそこにいた人たちと静岡弁の話になった。このような話になると、ある年齢以上の人たちは止まらなくなる。
このとき静岡で時々使われる「ごせっぽい」と言う方言の意味を今まで勘違いしていたことを知った。「清々しない」と思っていたのはまったく逆で「清々する」が正しいと教えられた。語源は「ごしょぽい」(御所ぽい)で"公家さんの清々とした所作"からきたそうだ。
もっともっと勘違いしている多くの言葉があるかもしれないと反省した。
昨日の朝日・天声人語に方言について次のような面白い記事があった。(抜粋)
"宮城県栗原市が市民憲章を制定することになった。方言で文案をつくったが、不評に頭を痛めている。〈眼(まなぐ) 光をにらみ…腹ん中 熱(あ)っつぐ熱(あ)っつぐ…おれらいま風を切って走る〉。
これを市民にはかると、「東北の暗さが強調される」「田舎っぽい」といった否定的な意見ばかり目立ったそうだ。
「土地の暮らしと歴史がこもった言葉で独自性を」と、5人の制定委員は意気込んだ。方言学者からは「すばらしい」と励まされた。ところが、肝心の市民の胸には、あまり響いて
いないようだ。"
なかなかユニークな発想と思いますが、どちらの意見に賛同するか、難しい問題です。
Posted by 風車 at
21:11
│Comments(2)
2007年04月21日
BOX ART
県立美術館で開催中の「ボックスアート」展を見てきました。
「ボックスアート」ってなーに?と思う人が多いと思います。"ガンダム"などのロボットのプラモデルをご存知だと思います。またプラモデルのキットを購入して自分で作られた方も多いと思います。「ボックスアート」とはプラモデルキットが入っている箱の表面に書かれた箱絵のことです。

消費者の購買意欲を高める目的で画かれていた「ボックスアート」がパッケージ装飾と言う役割を超えて、作る過程で完成形を想いおこすための"資料"としてまた空想の世界を生み出す"素材"として発展してきたそうです。
戦艦、戦車他の戦時下のものからスーパーカー他の自動車、子どもたちが一度は夢中になった数多くのロボット、スペースシャトルなどのプラモデルを彩った「ボックスアート」約160点が展示されています。
また精密なプラモデルの前の時代の竹ひごで作った模型飛行や紙袋に入ったキットなどの展示もあり、子供の頃夢中になったことを思い出しました。
「ボックスアート」ってなーに?と思う人が多いと思います。"ガンダム"などのロボットのプラモデルをご存知だと思います。またプラモデルのキットを購入して自分で作られた方も多いと思います。「ボックスアート」とはプラモデルキットが入っている箱の表面に書かれた箱絵のことです。

消費者の購買意欲を高める目的で画かれていた「ボックスアート」がパッケージ装飾と言う役割を超えて、作る過程で完成形を想いおこすための"資料"としてまた空想の世界を生み出す"素材"として発展してきたそうです。
戦艦、戦車他の戦時下のものからスーパーカー他の自動車、子どもたちが一度は夢中になった数多くのロボット、スペースシャトルなどのプラモデルを彩った「ボックスアート」約160点が展示されています。
また精密なプラモデルの前の時代の竹ひごで作った模型飛行や紙袋に入ったキットなどの展示もあり、子供の頃夢中になったことを思い出しました。
Posted by 風車 at
20:00
│Comments(0)
2007年04月19日
「見当」違い
このところバレンや絵の具を版木に移すための"運び"と言う道具を作ったりして肝心の版画を制作することから離れていました。
以前に写真をパソコンのレタッチソフトを利用して処理すると面白い図になることを紹介しました。それは赤、青、緑の三色で表すのですが、今回の試みは3つの色を版画で彫り、合成することです。
貼付した写真を見てください。
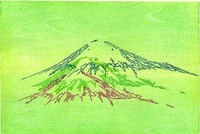 色刷り版画の場合、「見当」と称する"位置合せ"を使います。中央の緑が正式の位置です。次に赤を摺るときに、間違って別の「見当」を使ってしまったために緑から大幅にずれてしまいました。せっかくなので青を摺るときには意識的にずらしてみました。本来のものとは違いますがこれも面白いと自分では思っています。
色刷り版画の場合、「見当」と称する"位置合せ"を使います。中央の緑が正式の位置です。次に赤を摺るときに、間違って別の「見当」を使ってしまったために緑から大幅にずれてしまいました。せっかくなので青を摺るときには意識的にずらしてみました。本来のものとは違いますがこれも面白いと自分では思っています。
正式版はこちらです。光の青、赤、緑が重なると白くなるようですが、絵の具では当然変わってきます
なお、背景は版木の板目が出るように心がけたのですが、なかなかうまくいきませんでした。ちなみに大きさははがきサイズです。
以前に写真をパソコンのレタッチソフトを利用して処理すると面白い図になることを紹介しました。それは赤、青、緑の三色で表すのですが、今回の試みは3つの色を版画で彫り、合成することです。
貼付した写真を見てください。
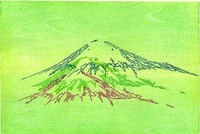 色刷り版画の場合、「見当」と称する"位置合せ"を使います。中央の緑が正式の位置です。次に赤を摺るときに、間違って別の「見当」を使ってしまったために緑から大幅にずれてしまいました。せっかくなので青を摺るときには意識的にずらしてみました。本来のものとは違いますがこれも面白いと自分では思っています。
色刷り版画の場合、「見当」と称する"位置合せ"を使います。中央の緑が正式の位置です。次に赤を摺るときに、間違って別の「見当」を使ってしまったために緑から大幅にずれてしまいました。せっかくなので青を摺るときには意識的にずらしてみました。本来のものとは違いますがこれも面白いと自分では思っています。正式版はこちらです。光の青、赤、緑が重なると白くなるようですが、絵の具では当然変わってきます

なお、背景は版木の板目が出るように心がけたのですが、なかなかうまくいきませんでした。ちなみに大きさははがきサイズです。
Posted by 風車 at
20:26
│Comments(0)
2007年04月17日
新聞の記事から・・・静岡県の事故統計
昨年まで住んでいた茨城県は交通事故が多く、交通マナーのあまり良くない印象を持っていた。静岡市に移って実際に運転したり歩いていて気がつくのは赤信号でも交差点を突きっていく車が意外に多いことである。
昨日の静岡新聞夕刊に、全国17の政令指定都市の人口10万人当りの人身事故件数と死者数のランキングが載っていた。
これによると浜松市は人身事故数1,229.8件、死者数6.06人でいずれも全国ワースト1位。静岡市はそれぞれ1,030.1件、5.50人でワースト3位、2位となっている。
浜松は今年4月に政令指定都市の仲間入りであるので、実質は静岡市がそれぞれのワースト2位,1位である。いずれにしても静岡市、浜松市の交通事故統計に驚いた。実際に県外より転入した方から「信号無視、無謀運転が多い」という指摘があるそうだ。
そして今日の朝刊には、昨年1年間の交通事故による県内の65歳以上の高齢ドライバーの死者数は48人という記事が載っていた。交差点内で23人、この中で出会い頭で10人が亡くなっており、交差点での一時停止とハンドル操作ミスのケースが多く、これは安全確認の不徹底と身体機能の衰えが要因と見られている。
一方、高齢ドライバーは信号無視やスピードの出し過ぎによる死亡事故は少なく、このことから「高齢者は信号やスピードなど一つのことであれば意識が働く。しかし自転車や歩行者、道路標識など複数のことを同時に注意する意識が薄い」と県警は分析している。
私自身、高齢ドライバーへの仲間入りにはあと2年ほどあるが年齢に関係なく、この記事をもう一度頭に入れて運転したい。"体が動き、判断の能力がある"と自分では理解していても、運転免許を返上する時期をそろそろ考えなくてはいけない年齢になってきた。
昨日の静岡新聞夕刊に、全国17の政令指定都市の人口10万人当りの人身事故件数と死者数のランキングが載っていた。
これによると浜松市は人身事故数1,229.8件、死者数6.06人でいずれも全国ワースト1位。静岡市はそれぞれ1,030.1件、5.50人でワースト3位、2位となっている。
浜松は今年4月に政令指定都市の仲間入りであるので、実質は静岡市がそれぞれのワースト2位,1位である。いずれにしても静岡市、浜松市の交通事故統計に驚いた。実際に県外より転入した方から「信号無視、無謀運転が多い」という指摘があるそうだ。
そして今日の朝刊には、昨年1年間の交通事故による県内の65歳以上の高齢ドライバーの死者数は48人という記事が載っていた。交差点内で23人、この中で出会い頭で10人が亡くなっており、交差点での一時停止とハンドル操作ミスのケースが多く、これは安全確認の不徹底と身体機能の衰えが要因と見られている。
一方、高齢ドライバーは信号無視やスピードの出し過ぎによる死亡事故は少なく、このことから「高齢者は信号やスピードなど一つのことであれば意識が働く。しかし自転車や歩行者、道路標識など複数のことを同時に注意する意識が薄い」と県警は分析している。
私自身、高齢ドライバーへの仲間入りにはあと2年ほどあるが年齢に関係なく、この記事をもう一度頭に入れて運転したい。"体が動き、判断の能力がある"と自分では理解していても、運転免許を返上する時期をそろそろ考えなくてはいけない年齢になってきた。
Posted by 風車 at
21:18
│Comments(2)
2007年04月16日
「写楽の謎」続き
先日、杉本章子さんの「写楽まぼろし」では"写楽は蔦屋重三郎の実の父"であるというストーリーを紹介したところ、このブログに時々、コメントを書いてくれる風魔さんが「東洲斎写楽について」と題する小冊子を見せてくれました。これは風魔さんの友人であるI.Yさんが26冊に及ぶ"写楽"に関する本を読んで"写楽は誰か"についてのまとめと自身の考えを述べたものです。一、二紹介します。
(1) 「東洲斎写楽はもういない」 (明石散人+佐々木幹雄著)
写楽=斉藤十郎兵衛 説
斉藤十郎兵衛は蜂須賀家のお抱えの喜多流地謡の長男として生まれ、後に地謡から春藤流ワキ方へ転向する。ここで歌舞伎役者の素顔を知り、趣味で書いた役者絵が評判となり、蔦重の耳に入る。約10ヶ月活躍したとき父の死により家を継ぐことになったが、絵筆を絶つことがその条件であったことから、忽然として消えざるを得なかった。
(2) 「写楽が現れた」 (TBS文化情報部と定村忠士)
東京・アダチ研究所が"北斎"の版木を調べていたところ「絵本東都遊」の色版木4枚の裏面に"写楽"の相撲絵「大童山土俵入り」の色版木の一部を発見した。ここで"写楽=北斎"との考え方が出てきたが、その後の調査で"北斎"の版木の裏に"歌麿"他の作品もあったことから、蔦重や職人たちにとっては"歌麿"も"北斎"もたいした問題ではなく、新らたに台頭した"北斎"のために古版木を削って再使用していたものと判明。
「大童山土俵入り」の絵から"写楽が"本所回向院の相撲を見に行った日を特定し、その日に回向院境内に行くことができなかった人(今まで写楽であると噂された人)は少なくとも"写楽"ではないと結論付けている。
この本は私も読みました。
I.Yさんは、自身が得た知識から考えると、"写楽"は斉藤十郎兵衛ではないかと推論しています。
これだけ多数の本、資料、展覧会から"写楽"に関する自身の考え方をまとめ、記録した熱意と努力に敬意を表します。
(1) 「東洲斎写楽はもういない」 (明石散人+佐々木幹雄著)
写楽=斉藤十郎兵衛 説
斉藤十郎兵衛は蜂須賀家のお抱えの喜多流地謡の長男として生まれ、後に地謡から春藤流ワキ方へ転向する。ここで歌舞伎役者の素顔を知り、趣味で書いた役者絵が評判となり、蔦重の耳に入る。約10ヶ月活躍したとき父の死により家を継ぐことになったが、絵筆を絶つことがその条件であったことから、忽然として消えざるを得なかった。
(2) 「写楽が現れた」 (TBS文化情報部と定村忠士)
東京・アダチ研究所が"北斎"の版木を調べていたところ「絵本東都遊」の色版木4枚の裏面に"写楽"の相撲絵「大童山土俵入り」の色版木の一部を発見した。ここで"写楽=北斎"との考え方が出てきたが、その後の調査で"北斎"の版木の裏に"歌麿"他の作品もあったことから、蔦重や職人たちにとっては"歌麿"も"北斎"もたいした問題ではなく、新らたに台頭した"北斎"のために古版木を削って再使用していたものと判明。
「大童山土俵入り」の絵から"写楽が"本所回向院の相撲を見に行った日を特定し、その日に回向院境内に行くことができなかった人(今まで写楽であると噂された人)は少なくとも"写楽"ではないと結論付けている。
この本は私も読みました。
I.Yさんは、自身が得た知識から考えると、"写楽"は斉藤十郎兵衛ではないかと推論しています。
これだけ多数の本、資料、展覧会から"写楽"に関する自身の考え方をまとめ、記録した熱意と努力に敬意を表します。
Posted by 風車 at
20:59
│Comments(0)
2007年04月15日
グランシップサポーター研修会
年度始めということで「グランシップサポーターの総会・研修会」が行われました。
総会といっても特別なことはなく、館長の挨拶(新館長はまだNHKと兼任で出席できず)、担当者の紹介、講演会、連絡事項で1時間半ほどで終了しました。
講演会は、グランシップでは5月の連休に子供たちを対象とした集いやお遊びがあるので、「子供たちにどのように対応すべき」かについて常葉学園短大・長橋助教授が、また「保育園・幼稚園の現場で感じたこと」について加藤寿子さんから話がありました。
長橋先生の「子どもたちとのコミュニケーション」と題した講演の要旨は以下のとおりです。
(1)子供たちを取り巻く環境は個々の環境によって異なるので当然、物に対する価値感覚も変わってくる。また、受け入れる情報もTV、ラジオ、ゲームなどのマスメディアだけの場合や天気予報など自然現象を知ろうとするなどの相違がある。
(2)人的環境としては、子供を尊重することから始めるべきで、考え方、やっていることを認める必要がある。遊びとか造形活動では必ずしもルールにはめる必要はない。個性を生かし延ばすことが重要。指導者としての意識を捨てて、言葉のキャッチボールから入って、子供の緊張感を和らげ、距離感を近づけること。同じ目線で対応し、一緒に考えるという共同者としての立場が良い。
(3)造形活動(遊び)を通しての対応は、子供の失敗を認めてどのように対処するかをともに考えることが必要で、他の子供との比較は控え、個性的部分の抽出し、評価してあげる。
ちょっと理解しがたい点もありますが、これはサポーターとしてイベントなどで子供さんに対応すべきときの基本的考え方として話されたようです。
私も県立美術館・実技室のお手伝いで子どもさんと接触する機会があります。この意見を参考にしたいと思います。
加藤さんは、今の若い親御さんは兄弟が少なく、また核家族を経験してきているので、「子育て」に関して"聞く"手段を持たない、周囲に相談する人がいないと言っておられました。つまり孤立しているので「子育て」が「孤育て」になってしまっている、ということです。親が何をして良いかわからない時代であり、保育の世界では「親育て」が必要という意見が出ているそうです。
"本当なの?"と言う気もしますが、専門家からの厳しいお話でした。
総会といっても特別なことはなく、館長の挨拶(新館長はまだNHKと兼任で出席できず)、担当者の紹介、講演会、連絡事項で1時間半ほどで終了しました。
講演会は、グランシップでは5月の連休に子供たちを対象とした集いやお遊びがあるので、「子供たちにどのように対応すべき」かについて常葉学園短大・長橋助教授が、また「保育園・幼稚園の現場で感じたこと」について加藤寿子さんから話がありました。
長橋先生の「子どもたちとのコミュニケーション」と題した講演の要旨は以下のとおりです。
(1)子供たちを取り巻く環境は個々の環境によって異なるので当然、物に対する価値感覚も変わってくる。また、受け入れる情報もTV、ラジオ、ゲームなどのマスメディアだけの場合や天気予報など自然現象を知ろうとするなどの相違がある。
(2)人的環境としては、子供を尊重することから始めるべきで、考え方、やっていることを認める必要がある。遊びとか造形活動では必ずしもルールにはめる必要はない。個性を生かし延ばすことが重要。指導者としての意識を捨てて、言葉のキャッチボールから入って、子供の緊張感を和らげ、距離感を近づけること。同じ目線で対応し、一緒に考えるという共同者としての立場が良い。
(3)造形活動(遊び)を通しての対応は、子供の失敗を認めてどのように対処するかをともに考えることが必要で、他の子供との比較は控え、個性的部分の抽出し、評価してあげる。
ちょっと理解しがたい点もありますが、これはサポーターとしてイベントなどで子供さんに対応すべきときの基本的考え方として話されたようです。
私も県立美術館・実技室のお手伝いで子どもさんと接触する機会があります。この意見を参考にしたいと思います。
加藤さんは、今の若い親御さんは兄弟が少なく、また核家族を経験してきているので、「子育て」に関して"聞く"手段を持たない、周囲に相談する人がいないと言っておられました。つまり孤立しているので「子育て」が「孤育て」になってしまっている、ということです。親が何をして良いかわからない時代であり、保育の世界では「親育て」が必要という意見が出ているそうです。
"本当なの?"と言う気もしますが、専門家からの厳しいお話でした。
Posted by 風車 at
20:47
│Comments(1)
2007年04月14日
「坐漁の人」「空っ風」諸田玲子の作品
2月に諸田玲子さんの講演会に行ったことはここに書きましたが、その作品についてはあまり読んでなかったので今回タイトルに記した2冊の本を読みました。
いずれも静岡、というか清水、由比、興津に関する短編と、後者は清水の次郎長一家の中では有名であったが、あまり取り上げられなかった「小政」の次郎長との出会いから確執について書かれたものです。
「坐漁の人」の短編は「由比正雪」と明治の元老「西園寺公望」暗殺の企てのほか次郎長に関連した「2代目お蝶」と「大政」のお話です。
これらの小説は作家の考えを基にしたフィクションですから史実がどうであったかは別問題です。
昨日、清水区港橋そばの次郎長が経営したという船宿「末廣」に入ってみました。ここは2度目ですが、中の店員の女性がとても親切に「次郎長」のことを説明してくれます。

1Fには等身大の次郎長の人形や次郎長と山岡鉄舟を結びつける遠因となった"咸臨丸"の模型、2Fには英語塾の様子などが展示されています。
子供の頃の東映映画で見た「東海道の侠客」だけの次郎長だったらこんなに人気は出なかったでしょう。明治維新の転身が今日の伝説を作り、その意味で先見の明のあった人だと思います。
また、その成功には3代目「お蝶」さんのコントロールも見逃せないようです。
いずれも静岡、というか清水、由比、興津に関する短編と、後者は清水の次郎長一家の中では有名であったが、あまり取り上げられなかった「小政」の次郎長との出会いから確執について書かれたものです。
「坐漁の人」の短編は「由比正雪」と明治の元老「西園寺公望」暗殺の企てのほか次郎長に関連した「2代目お蝶」と「大政」のお話です。
これらの小説は作家の考えを基にしたフィクションですから史実がどうであったかは別問題です。
昨日、清水区港橋そばの次郎長が経営したという船宿「末廣」に入ってみました。ここは2度目ですが、中の店員の女性がとても親切に「次郎長」のことを説明してくれます。

1Fには等身大の次郎長の人形や次郎長と山岡鉄舟を結びつける遠因となった"咸臨丸"の模型、2Fには英語塾の様子などが展示されています。
子供の頃の東映映画で見た「東海道の侠客」だけの次郎長だったらこんなに人気は出なかったでしょう。明治維新の転身が今日の伝説を作り、その意味で先見の明のあった人だと思います。
また、その成功には3代目「お蝶」さんのコントロールも見逃せないようです。
Posted by 風車 at
20:23
│Comments(0)
2007年04月12日
血圧、コレステロール
40歳代前半から血圧(最小血圧)、コレステロールに関して医師から注意を受けてきた。医師のアドバイスどおりタバコを止めたり、食事に注意したりしてきたが薬なしでは基準値には入らない。ただ家系的にも高血圧、高コレステロールの傾向があるので体質によるものと半分は決め付けている。それでも退職後はさすがにストレスがなくなってきたのか、週末肩が張るという現象はなくなった。
2,3年前、血圧が安定してきたので薬を飲むことを"自主的に止めた"ら次の検診では見事に上昇していた。薬のお世話になると薬を止めることはできないそうだ。
幸い、昨年初めごろから体質にマッチした薬が見つかって、最近は血圧、総コレステロール値、悪玉コレステロール値も何とか基準に収まっている。
今日は3ヵ月毎の検診だったが、静岡に来てからは病院が"予約制"となっているのがありがたい。なんせこのての診察は血圧を測るだけ(血液検査の結果を聞くこともあるが)なので、5分くらいで終わってしまう。茨城にいたときはとにかく待たされてそれだけで血圧が上がってしまったものだ。
いまメタボリックシンドロームが注目されているが、男性の腹回り85cmの基準は私にとってもちょっと厳しい。ウエストサイズだったら十分パスするのだが・・・
2,3年前、血圧が安定してきたので薬を飲むことを"自主的に止めた"ら次の検診では見事に上昇していた。薬のお世話になると薬を止めることはできないそうだ。
幸い、昨年初めごろから体質にマッチした薬が見つかって、最近は血圧、総コレステロール値、悪玉コレステロール値も何とか基準に収まっている。
今日は3ヵ月毎の検診だったが、静岡に来てからは病院が"予約制"となっているのがありがたい。なんせこのての診察は血圧を測るだけ(血液検査の結果を聞くこともあるが)なので、5分くらいで終わってしまう。茨城にいたときはとにかく待たされてそれだけで血圧が上がってしまったものだ。
いまメタボリックシンドロームが注目されているが、男性の腹回り85cmの基準は私にとってもちょっと厳しい。ウエストサイズだったら十分パスするのだが・・・
Posted by 風車 at
21:08
│Comments(0)
2007年04月11日
船越堤公園のサギ
清水区・船越堤公園には雄池、雌池の2つの池がある。
そして雌池の対岸の林に一羽のサギ(?)が棲んでいる。昨年は散歩の途中、松にとまって釣り人を眺めている姿を良く見かけたが、最近見ることがなく心配していた。
今日も池の北側斜面に借りている畑で知人とその話をしていたら、林の中から飛来してきて池に急降下。一匹の魚を咥えて飛び立って、いつもの松に戻ってかなり大きな魚を飲み込んでいた。
久しぶりに見る姿に知人、妻とも"ほっ"一息。今まではもっと黒い感じであったが、羽が生え変わったのであろうか、白くなったような気がする。
池というより公園の主のように思えるし、釣り人にもとても慣れているそうだ。とにかく元気な姿が見られて良かった。
そして雌池の対岸の林に一羽のサギ(?)が棲んでいる。昨年は散歩の途中、松にとまって釣り人を眺めている姿を良く見かけたが、最近見ることがなく心配していた。
今日も池の北側斜面に借りている畑で知人とその話をしていたら、林の中から飛来してきて池に急降下。一匹の魚を咥えて飛び立って、いつもの松に戻ってかなり大きな魚を飲み込んでいた。
久しぶりに見る姿に知人、妻とも"ほっ"一息。今まではもっと黒い感じであったが、羽が生え変わったのであろうか、白くなったような気がする。
池というより公園の主のように思えるし、釣り人にもとても慣れているそうだ。とにかく元気な姿が見られて良かった。
Posted by 風車 at
21:31
│Comments(0)
2007年04月10日
グランシップでのサポーター業務始まる
今日からグランシップでのサポーター(ボランティア)業務が始まりました。
曜日ごとに2つのグループがあり、私はBグループの火曜日担当で、男女それぞれ3人の計6名のグループです。最高齢者は82歳の男性ですが、とても元気で私にいろいろなことを教えてくれました。
本日の業務は昨日の夕刊、今日の朝刊各紙に掲載されている「グランシップ」関係、県内の伝統文化、ボランティアに関するものなどの記事の切抜きを作ることと、グランシップから関係各位に送られる今年度のスケジュールなどの郵送準備でした。
新年度が始まったばかりで、今はこれら郵送物が非常に多く、サポータの中心業務になっているようです。また、5月の連休に行われる各種行事の準備も行いました。
今までのボランティアはゴルフトーナメントのギャラリー整理や町で主催したパソコン講座の補助、静岡では美術館実技室でのお手伝いなどどちらかというと体力を使うことが多かったのですが、今回の業務は机上作業が多いことが特徴です。
今後月2回のペースで行います。
曜日ごとに2つのグループがあり、私はBグループの火曜日担当で、男女それぞれ3人の計6名のグループです。最高齢者は82歳の男性ですが、とても元気で私にいろいろなことを教えてくれました。
本日の業務は昨日の夕刊、今日の朝刊各紙に掲載されている「グランシップ」関係、県内の伝統文化、ボランティアに関するものなどの記事の切抜きを作ることと、グランシップから関係各位に送られる今年度のスケジュールなどの郵送準備でした。
新年度が始まったばかりで、今はこれら郵送物が非常に多く、サポータの中心業務になっているようです。また、5月の連休に行われる各種行事の準備も行いました。
今までのボランティアはゴルフトーナメントのギャラリー整理や町で主催したパソコン講座の補助、静岡では美術館実技室でのお手伝いなどどちらかというと体力を使うことが多かったのですが、今回の業務は机上作業が多いことが特徴です。
今後月2回のペースで行います。
Posted by 風車 at
20:46
│Comments(0)
2007年04月09日
18キップでお城巡り
先週末、妻が風邪で寝込んでしまい予定していた友人との遠出ができなくなりました。そこで有効期限が迫った18キップの処理のため、一人で浜松、掛川を巡ってきました。
浜松では旧東海道の史跡を歩き、浜松城公園へ。見上げる天守閣と散って落ちてくる桜の花の組合せはなかなかのものでした。
家康が築城したとのことで、ここにも家康像がありました。ただし、家康が在城したのは1570年からの16年間なので、静岡の駿府公園のものと比べるとだいぶ若々しい銅像です。ちなみに"家康お手植えのみかん"もありました。

浜松の街を歩いて気付いたことですが大きな道路に"横断歩道"が少なく、"地下通路"が多いことです。すっきりしていて車には良いのですが、昇降が多く、これからの高齢化社会が心配です。
JRで少し戻って掛川城を見ました。山内一豊で有名な城ですが、安政の大地震で崩壊し、今の城は平成6年に再建されたとのことでした。構造的には昔の再現ですが、新しさを感じました。彦根城と同じく、天守閣に登る階段は狭くて急勾配でした。

二の丸にあった城御殿は地震後に再建された書院造りで数多くの畳部屋からなっており、部屋の中に入って見ることもでき、こちらのほうが歴史を感じました。
今朝は5時ごろからマスターズのゴルフ中継を見ていたので帰りの電車では疲れと相まってぐっすりと眠りました。
浜松では旧東海道の史跡を歩き、浜松城公園へ。見上げる天守閣と散って落ちてくる桜の花の組合せはなかなかのものでした。
家康が築城したとのことで、ここにも家康像がありました。ただし、家康が在城したのは1570年からの16年間なので、静岡の駿府公園のものと比べるとだいぶ若々しい銅像です。ちなみに"家康お手植えのみかん"もありました。

浜松の街を歩いて気付いたことですが大きな道路に"横断歩道"が少なく、"地下通路"が多いことです。すっきりしていて車には良いのですが、昇降が多く、これからの高齢化社会が心配です。
JRで少し戻って掛川城を見ました。山内一豊で有名な城ですが、安政の大地震で崩壊し、今の城は平成6年に再建されたとのことでした。構造的には昔の再現ですが、新しさを感じました。彦根城と同じく、天守閣に登る階段は狭くて急勾配でした。

二の丸にあった城御殿は地震後に再建された書院造りで数多くの畳部屋からなっており、部屋の中に入って見ることもでき、こちらのほうが歴史を感じました。
今朝は5時ごろからマスターズのゴルフ中継を見ていたので帰りの電車では疲れと相まってぐっすりと眠りました。
Posted by 風車 at
19:38
│Comments(2)
2007年04月07日
バレン作り
版画を摺るときに使うバレンは竹の皮に包まれています。長い間の使用や使い方によって表面の竹の皮が破れてきます。したがって竹皮でのバレンの包み方を練習しておく必要があります。
そんなことから数日前から本を読んで「包み方」の勉強をしていましたが、いっそのことゼロから作り直してみようと挑戦してみました。
バレンのあて板にはベニヤ板(本ではアクリル板)、芯は水糸(タコ糸)を「観世縒り」3回繰り返して作った紐を渦巻状に巻きます。この「観世縒り」が大変。1回縒るとほどけてしまいます。結局電動ドリルの先端に縒るための治具を取り付けてなんと完成。写真は竹の皮で包む前の姿です。

縒った紐の”ごつごつ"感が摺りに影響を与えるとのこと。これで実際に版画を摺ってみたところ、さすがに購入品のレベルまでは届きませんでしたが、結構上手に摺れました。
自分で"物"を作って、使ってみる楽しみを味わいました。
そんなことから数日前から本を読んで「包み方」の勉強をしていましたが、いっそのことゼロから作り直してみようと挑戦してみました。
バレンのあて板にはベニヤ板(本ではアクリル板)、芯は水糸(タコ糸)を「観世縒り」3回繰り返して作った紐を渦巻状に巻きます。この「観世縒り」が大変。1回縒るとほどけてしまいます。結局電動ドリルの先端に縒るための治具を取り付けてなんと完成。写真は竹の皮で包む前の姿です。

縒った紐の”ごつごつ"感が摺りに影響を与えるとのこと。これで実際に版画を摺ってみたところ、さすがに購入品のレベルまでは届きませんでしたが、結構上手に摺れました。
自分で"物"を作って、使ってみる楽しみを味わいました。
Posted by 風車 at
21:22
│Comments(0)
2007年04月06日
メジャーリーグとマスターズ
MLBが開幕して、今朝は松坂投手が見事なデビューで初勝利。ニュースで結果を知っていたが、NHKBs放送の録画を食い入るように見た。
気温2℃という寒さの中、初回ピンチを招くもダプルプレーで切り抜け、徐々に調子を上げて4連続三振など、いつもの彼のペース。6回にホームランを浴び、さらに二塁打などでちょっと心配させたが、期待通りの活躍。
次回はイチロー、城島選手のいるマリナーズ戦で登板するとのこと、楽しみ。
この放送の前にはライブでN.ヤンキースとT.デビルレイズ戦が中継されており、雪が舞うヤンキースタジアムでは松井選手の同点タイムリーの後、ヤクルトから移った岩村選手が二塁打を打ち、決勝のホームを踏んでデビルレイズが勝った。
野球では日本選手の活躍が目立つ一日だった。
一方、フロリダのオーガスタで始まったマスターズゴルフ。美しいグリーン周りと選手を悩ます高速かつ複雑なグリーンに名手たちが挑戦する4日間が始まった。
しかし、日本選手の初日は今年も低迷。世界の一流との違いを痛感する。
タイガーウッズ選手他やギャラリー(マスターズではパトロンと呼ぶそうだが・・・)は半そで姿。アメリカ大陸の大きさが良くわかる。
気温2℃という寒さの中、初回ピンチを招くもダプルプレーで切り抜け、徐々に調子を上げて4連続三振など、いつもの彼のペース。6回にホームランを浴び、さらに二塁打などでちょっと心配させたが、期待通りの活躍。
次回はイチロー、城島選手のいるマリナーズ戦で登板するとのこと、楽しみ。
この放送の前にはライブでN.ヤンキースとT.デビルレイズ戦が中継されており、雪が舞うヤンキースタジアムでは松井選手の同点タイムリーの後、ヤクルトから移った岩村選手が二塁打を打ち、決勝のホームを踏んでデビルレイズが勝った。
野球では日本選手の活躍が目立つ一日だった。
一方、フロリダのオーガスタで始まったマスターズゴルフ。美しいグリーン周りと選手を悩ます高速かつ複雑なグリーンに名手たちが挑戦する4日間が始まった。
しかし、日本選手の初日は今年も低迷。世界の一流との違いを痛感する。
タイガーウッズ選手他やギャラリー(マスターズではパトロンと呼ぶそうだが・・・)は半そで姿。アメリカ大陸の大きさが良くわかる。
Posted by 風車 at
19:48
│Comments(0)
2007年04月05日
読書感「写楽まぼろし」杉本章子
題名からは"写楽"のことかと思わせるが、内容は江戸・寛政時代の文化を裏で支えた"版元・蔦屋重三郎"の物語。

"歌麿"を育て上げ、版元として地位を築き上げる一方、寛政の改革で身代を半分に減らされるなか、まだ見ぬ"写楽"を追い続ける重三郎の姿と彼を取り巻く人々が画かれている。
突如として現れ、忽然として消えた"写楽"の存在については諸説あるようだが、この作品では幼い頃自分を捨てた"父"に結びつけ、"写楽"後期の作品の変化や落款が"東洲斎写楽画”から"写楽画"に変わった謎解きも行っている。
また、歌麿が画いた「歌撰恋之部 物思恋」は重三郎の恋人"おしの"であることや前半からの登場人物が後半にいろいろな関係を持ってつながる面白さなどもあり、フィクションとして充分に楽しめた。

"歌麿"を育て上げ、版元として地位を築き上げる一方、寛政の改革で身代を半分に減らされるなか、まだ見ぬ"写楽"を追い続ける重三郎の姿と彼を取り巻く人々が画かれている。
突如として現れ、忽然として消えた"写楽"の存在については諸説あるようだが、この作品では幼い頃自分を捨てた"父"に結びつけ、"写楽"後期の作品の変化や落款が"東洲斎写楽画”から"写楽画"に変わった謎解きも行っている。
また、歌麿が画いた「歌撰恋之部 物思恋」は重三郎の恋人"おしの"であることや前半からの登場人物が後半にいろいろな関係を持ってつながる面白さなどもあり、フィクションとして充分に楽しめた。
Posted by 風車 at
20:47
│Comments(0)
2007年04月04日
優勝 おめでとう
昨日、静岡では常葉菊川高校の選抜高校野球大会優勝で大いに盛り上がりました。静岡県勢の選抜優勝は浜松商業以来29年ぶりとのこと。
静岡新聞の夕刊のコラム「窓辺」は県内在住の著名人が2ヶ月間、週1回の担当でさまざまなことを書いてくれています。先月まで担当されていた方の一人に駒澤大学野球部で指導された太田元監督おり、最後のコラムで"静岡県の野球レベルの衰退"について書かれていましたが、この記事に菊川ナインが発奮したのかどうかはわかりませんが、県民に勇気を与える優勝だったと感じます。
全試合をTVで見たわけではないし、専門家でもありませんが、一ファンとして今回の優勝のポイントの一つは仙台育英高校との緒戦、9回1点リードの場面で無死(1死?)三塁で投手交代、リリーフが後続を断ち切ったことがあげられると思います。
今までの静岡県のチームだと往々にして浮き足立ち、同点あるいは逆転されてしまうケースが多かったと思いますが、あの場面での図太さが"このチームはちょっと違う"と感じさせました。
準決勝、決勝戦の後半での逆転劇も"従来の静岡県のチームらしさ"とは違う力強さでした。
監督さんはTVで見るとやさしそうですが、練習ではとても厳しいそうです。部員の皆さん、少しだけのんびりして、また夏に向かって練習で監督さんに絞られて、静岡県勢初の春夏連覇を目指してください。
また他の高校も"打倒・常葉菊川!!"を目指し練習に励んで、野球王国を復活してください。
静岡新聞の夕刊のコラム「窓辺」は県内在住の著名人が2ヶ月間、週1回の担当でさまざまなことを書いてくれています。先月まで担当されていた方の一人に駒澤大学野球部で指導された太田元監督おり、最後のコラムで"静岡県の野球レベルの衰退"について書かれていましたが、この記事に菊川ナインが発奮したのかどうかはわかりませんが、県民に勇気を与える優勝だったと感じます。
全試合をTVで見たわけではないし、専門家でもありませんが、一ファンとして今回の優勝のポイントの一つは仙台育英高校との緒戦、9回1点リードの場面で無死(1死?)三塁で投手交代、リリーフが後続を断ち切ったことがあげられると思います。
今までの静岡県のチームだと往々にして浮き足立ち、同点あるいは逆転されてしまうケースが多かったと思いますが、あの場面での図太さが"このチームはちょっと違う"と感じさせました。
準決勝、決勝戦の後半での逆転劇も"従来の静岡県のチームらしさ"とは違う力強さでした。
監督さんはTVで見るとやさしそうですが、練習ではとても厳しいそうです。部員の皆さん、少しだけのんびりして、また夏に向かって練習で監督さんに絞られて、静岡県勢初の春夏連覇を目指してください。
また他の高校も"打倒・常葉菊川!!"を目指し練習に励んで、野球王国を復活してください。
Posted by 風車 at
18:15
│Comments(1)



